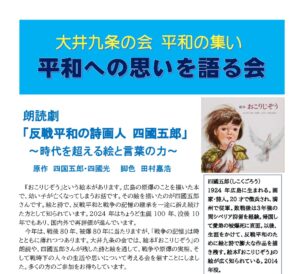戦争を起こす人間に対して、本気で怒れ
大井九条の会では、毎年8月に平和の集いを開催し、戦争の記憶の継承に取り組んできた。戦後80年・被爆80年を迎え、戦争を体験した人が減り戦争の記憶が薄れていく一方で、軍備拡大による「戦争ができる国」化が急激に進行している今、戦争の実相を知り「戦争の記憶」を継承する活動はますます重要になっている。
今年の平和の集いでは、絵と詩で反戦平和を訴え続けた四國五郎を取り上げる。四國五郎と言っても、絵本『おこりじぞう』の絵を描いた人ぐらいの認識でほとんどの人が知らないと思うが、出身地の広島では被爆地「ヒロシマ」を描き続けた人としてなじみのある人物である。四國五郎は、広島の貧農の家に生まれ、将来は画家をめざしていたが、家の貧しさと戦争のために断念する。20歳で徴兵され満州で従軍し、敗戦後は3年強の間捕虜としてシベリアで抑留生活を送る。24歳の時に帰国するが、最愛の弟が被爆死したことを知る。戦争に行き死ぬはずの自分が生き残り、広島に残り生きるはずの弟が原爆で死んでしまった。そのことに苦しみ、深い悲しみと怒りを抱いた四國五郎は、死者にかわって平和のために絵を描こうと決心する。満州での戦闘からシベリア抑留に至る自身の戦争体験と、弟の予期せぬ被爆死が、心の中で一直線の因果関係で繋がったからである。すべては、戦争という国家が推進した巨大な暴力によって引き起こされた。為政者の間違った政治判断が、罪のない膨大な人々を死に追いやったのだ、と。
四國五郎が、自分の幼い子どもに何度も言い聞かせた言葉がある。
「つまらんことで怒るんじゃない。悪い人間は沢山いる。だけど世の中には本当に悪い人間というのがいる。それは戦争を起こす奴だ。戦争は台風や地震みたいな自然災害じゃない。人間が起こすもんだ。もの凄い数の人間が不幸になる。だから、つまらんことで怒るんじゃなくて、戦争を起こすような、本当に悪い人間に対して、本気で怒れ。」
「平和のために絵を描く」という決心は、単に「平和」をテーマとした絵を描くという話ではなく、「生き方」の問題として、そのような目的を持った絵と詩を創る人生を生きることを自分に課したということである。四國五郎が作った「心に喰い込め」という詩の中に次のような一節がある。
「この黒い土がいつまでも黒いように/人々の戦争を憎む気持ちをかえさせまい/いつまでもかえさせまい!/中略/ものいわぬ黒い土よ/かえらない人々よ/弟よ/地上の人のこころに/私のこころに/喰い込め!/ふかく喰い込め!」
四國五郎が帰国した翌年から朝鮮戦争が始まり、日本の再軍備が始まる。GHQによる言論統制が続く厳しい時代に、四國は『原爆詩集』で有名な峠三吉たちと「われらの詩の会」という市民サークルを結成し、反戦・反核の表現活動に取り組んでいく。機関誌『われらの詩』の創刊、『反戦詩歌集』の発行、街なかでの「辻詩」という反戦活動の中で、四國は表紙画・挿絵・ポスターを描いたり、詩や評論を積極的に発表している。 また、1974年にNHK広島が企画した「市民の手で原爆の絵を残そう」というプロジェクトに絵の描き方の指導という立場で協力している。このプロジェクトはわずか2年間で2225枚の絵が寄せられ、それまで知られていなかった原爆投下時の実相や被爆者の思いが明らかになるきっかけとなった。 四國自身も、峠三吉たちとの活動や寄せられた多くの被爆者の絵に関わることで、戦争や原爆の実相に対する理解が深まり、それが絵や詩に結実されるようになる。1980年の原水爆禁止世界大会の会場で四國が作り自らが朗読した「ひろしまの子」という長い詩がある。
「あなたの隣を見てください ひろしまの子がいませんか/中略/ ひろしまの少年少女達は/中略/およそ人間の頭で考えられる一番むごたらしい死にざまで 死にました/中略/被爆者援護法もよそに なりふりかまわぬ軍備増強白書が伝えられた今日/ひろしまの子は わたしに寄り添い じっとわたしをみつめているのです/中略/その瞳にこたえてやってください/あなたの目で うなずきかえしてやってください/ひろしまの子に わかるように/けっして再び あやまちをくり返さないと!/けっして 許さないと!」
7月の参院選で「核武装が安上がりで、一番安全だ」と主張した候補者がいる政党が大幅に議席を増やした。また、世界に目を転じれば、力による支配と対立が広がっている。国内外の厳しい情勢の中で戦後80年を迎えるにあたって、新たな決意を持って反戦平和の活動に取り組んでいきたい。
大井九条の会代表 田村嘉浩